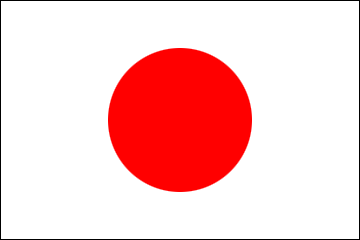スロバキア短信 11 「バンスカー・ビストリツァとバンスカー・シュティアウニツァ」

スロバキアには行政区画として8つの県があり,国の中部にあるバンスカー・ビストリツァ県は8県中最大の面積を有します。山形県や青森県くらいの広さです。人口は県全体で65万人,バンスカー・ビストリツァ市が8万人,バンスカー・シュティアウニツァ市が1万人くらいです。地勢としては,山地が多いのが特徴です。現在使われているスロバキア語の標準語は中部地方の方言を基にしていると言われています。
バンスカー・ビストリツァ(Banská Bystrica)
バンスカー・ビストリツァ県の県庁所在地です。「バンスカー」はスロバキア語で鉱山のとか,鉱業のという意味です。名前が示すとおり,バンスカー・ビストリツァはかつて鉱山業,特に銅で栄えた町です。銅の採掘に使われた紀元前の道具が出土していますが,中世以降,本格的に採掘されるようになり,ヨーロッパにおける銅の首都と言われるほど繁栄しました。15世紀末には大規模な鉱山会社が作られ,従業員に対する医療サービスを提供するなど当時としては先進的な企業だったようです。この会社は,採掘・製錬だけでなく銅製品も製造していました。しかし,18世紀までに銅資源がほぼ枯渇,銅産業は衰退し,20世紀初頭には消滅しました。
バンスカー・ビストリツァは,スロバキア現代史上の重要な出来事と深く関わっています。第二次世界大戦前夜の1938年から39年にかけて,ナチス・ドイツが周辺国に触手を伸ばす過程で,チェコスロバキア共和国は,チェコとスロバキアとに分かれることとなりました。チェコはドイツの保護領となり(一部はドイツ領に編入),事実上ドイツの支配下に置かれました。スロバキアはチェコスロバキアから分離独立して独立は維持したものの,実質的にはドイツの従属国となり,ナチズムが採り入れられました。このため第二次大戦では,スロバキアはドイツに組することとなりました。他方,多くのスロバキア軍人が祖国を離れて連合軍に参加し,ヨーロッパ各地の戦線で連合軍と一緒に戦いました。
スロバキア国内では,反政府・反ナチのレジスタンスが起こり,1944年8月29日,大規模な武装蜂起が行われましたが,その拠点となったのがバンスカー・ビストリツァです。当時,ヨーロッパ最大規模の反ナチ武装蜂起となりました。バンスカー・ビストリツァが拠点とされたのは,スロバキアの中心に位置するという戦略的理由もあったそうです。この武装蜂起は間もなくドイツ軍によって鎮圧され,この後,スロバキアはドイツ軍に占領されます。1945年4月にソ連軍とルーマニア軍によってスロバキアがナチス・ドイツから解放されるまでレジスタンス勢力は山間部にこもって抵抗を続けました。
毎年8月29日は「スロバキア民族蜂起の日」としてスロバキアの国の記念日となっています。この日の前後には,首都ブラチスラバでも,バンスカー・ビストリツァでも政府首脳が出席して記念の行事が行われます。また,バンスカー・ビストリツァには,「スロバキア民族蜂起博物館」があり,武装蜂起に関する展示を見ることができます。「スロバキア民族蜂起」はスロバキア語で約してSNPと呼ばれていますが,町の中心にある広場も「SNP広場」と命名されています。因みに,ブラチスラバにもSNP広場がありますし,ドナウ川に架かる橋の一つもSNP橋と名付けられています。
現在のバンスカー・ビストリツァは,学術や芸術の町でもあり,ブラチスラバ,コシツェと並ぶ3大オペラの一つ,バンスカー・ビストリツァ国立オペラがあります。この国立オペラは日本と深い関わりがあります。かつてスロバキアが被援助国であった時代,1996年に日本政府はバンスカー・ビストリツァ国立オペラに対して政府開発援助として音響機材を供与しました。これを契機として同オペラは日本との交流を始めることとなり,1999年以来今日まで毎年欠かさず日本へ公演旅行に出向き,北は北海道から南は与論島まで,日本全国を巡っています。これらすべての日本公演は,地元ボランティアや友好団体の協力を得て非商業ベースで行われており,公演だけでなく,地元の人々との交流会やオペラに関するセミナーを開催するなど,各地で友好親善を深めてきたのは,素晴らしいことだと思います。こうした同オペラの功績を称えて,今年5月に在外公館長表彰を行いました。

バンスカー・ビストリツァ国立オペラ劇場
(写真提供:国立オペラ)
バンスカー・シュティアウニツァ(Banská Štiavnica)
バンスカー・ビストリツァの南西,50キロくらいの位置にあります。バンスカー・シュティアウニツァも鉱山業で栄えた町です。スロバキア中部には,「バンスカー」の付く名前の都市がいくつもあり,この地域一帯で鉱山業が盛んであったことを示しています。スロバキア中部から東部に至る山地の名前はSlovenské rudohorie,日本語に訳すと「スロバキア鉱石山地」ということになり,これも鉱物資源が豊富であった証左でしょう。
バンスカー・シュティアウニツァでは銀や金が主でした。ここでも紀元前から採掘が行われ,中世以降ヨーロッパでも有数の銀山として栄え,1993年まで採掘されていましたが,現在は一帯の銀鉱はすべて閉山となっています。バンスカー・シュティアウニツァは,1993年に「バンスカー・シュティアウニツァ歴史都市と近隣の技術的建造物群」としてユネスコの世界遺産に登録されました。製錬所跡や坑道跡なども含まれています。スロバキアに7つある世界遺産の一つです。
この町には鉱山博物館があり,屋内外展示のほか,かつての坑道が展示用に公開されています。徒歩で坑道内を回るツアーがあって,坑道はツアー用に整備されてはいるものの,かなり原型をとどめていて,リアルな往時の坑道の様子を味わえます。ハンガリー王国(スロバキアは第一次世界大戦までハンガリー王国の一部でした)の国王マリア・テレジアの夫君が何度か鉱山を訪れたそうで,当時の銘板が坑道内に残っています。国家にとって重要な鉱山であった証だと思います。
バンスカー・シュティアウニツァにはかつて世界で初めて設立された鉱業学校もありました。この学校は1762年,国王マリア・テレジアの命により設立され,ヨーロッパだけでなく世界のにおける鉱山学・鉱山技術の中心となったそうです。第一次世界大戦の結果,チェコスロバキアがハンガリーから分離独立したため,1919年に学校はハンガリーに移されましたが,建物は現存しており,工業専門学校と植物園として使われています。
 |
 |
|
公開されている坑道跡
|
鉱業学校の建物 (写真提供:スロバキア鉱山博物館Lubomír Lužina 氏及びKatarína Patschová氏) |
バンスカー・シュティアウニツァでは,毎年9月に「サラマンダー祭り」が行われます。古くは鉱業学校の学生や教師が街を行進する行事だったのが,鉱山業に従事する技師や労働者の祭りとなり,現在は市を挙げての祭りとなっています。今年は,スロバキアのキスカ大統領が祭りを訪れました。サラマンダーはトカゲのことで,昔,一人の羊飼いが背に金粉と銀粉の輝く2匹のトカゲが岩から這い出るのを見て,岩を動かしてみると,金と銀が出てきたというこの地方に古くから伝わる伝説に因んでいます。2匹のトカゲはバンスカー・シュティアウニツァ市の古い紋章にも使われていたそうです。祭りの行進の先頭を務めるのは,トカゲ(の模型)を持った羊飼い(に扮した人)です。
この祭りには今でも数多くの鉱山関係者が祭りの主役といった感じで参加します。スロバキアの鉱山関係者は儀式などのときのための正装用の制服があり,祭りには大勢が制服で参加しています。金ボタンの制服で日本の中高生の伝統的な制服にちょっと似ています。かつてオスマン・トルコ軍が攻めてきたときに,最前線立って町を守ったのも鉱山関係者だったそうです。
 |
 |
|
サラマンダー祭り
(写真提供:スロバキア鉱山博物館Lubomír Lužina 氏及びKatarína Patschová氏) |
制服を着た鉱山関係者
(写真提供:スロバキア鉱山博物館Lubomír Lužina氏及びKatarína Patschová氏) |
バンスカー・シュティアウニツァ市は,2008年に秋田県小坂町と交流のための協定を結んでいます。小坂町もかつて日本有数の鉱山であった小坂鉱山を擁する町です。
日本とスロバキアの間の正式な自治体交流としては,この他に,奈良県野迫川(のせがわ)村とヴィソケー・タトリ市(プレショウ県)が姉妹都市となっています。自治体交流に限らず,ビジネス,文化・芸術,学術,スポーツ等様々な分野での人的交流の積み重ねが両国間の友好関係に結び付いており,大使館としても,できる限りそうした交流のお手伝いをさせていただきたいと考えています。
2015年10月
在スロバキア特命全権大使
江川明夫