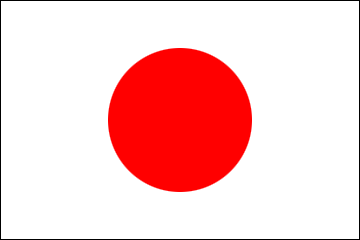第十一話 ヨーロッパ冬の風物詩「ザビーヤチカ」(豚の一匹解体)
平成28年11月18日

「先日ザビーヤチカに行ってきた」と首都ブラチスラバ在留のスロバキア人に言ったら、「えっ。今でもまだザビーヤチカやってるの?」と驚かれました。
「ザビーヤチカ」とはスロバキア語の「殺す(ザビッチ)」という単語に語源があります。スロバキアの村の農家の伝統的行事で、秋から冬に向かうちょうど今頃、自宅で飼っている豚を一匹落として(殺して)解体し、主として自家用の、ハムやベーコン、ソーセージなどの保存食を作る家族の「お祭り」です。
農家にとって豚は大事な売り物でもあり、財産です。それを冬を前に一匹「落として」しまうのは、昔は冬になると食料も乏しくなり、また暖房施設も今のようにないので、家族一同、栄養豊富でカロリーも高い豚肉を保存食として作り、それを食べて、いわば体の中から温めて寒い冬を乗りきる必要があったから、と言われています。更に、牧草や藁を食べて育つ牛や羊と異なり、豚は穀物や芋といった人間と同じような食べ物をとって大きくなるので、ただでさえ食料が乏しくなる冬の間は、食い扶持(食いブタ?)を少しでも減らしてその豚自身を食べてしまおう、という思惑もあったのではないか、とも思われます。
1993年のチェコスロバキアからのスロバキアの分離・独立、更にはその後の急速な経済発展により、スロバキア人は相対的に豊かになりました。スーパーマーケットには年中食べ物があふれ、建物には電気、ガス等の暖房設備が整備されるようになりました。そんな中で、スロバキア人の多くにとって、わざわざ冬前にザビーヤチカで豚を落として保存食を作る必要性はなくなってしまいました。また、スロバキア経済に占める農業生産の割合が3.74%(2014年統計)に減少する中、地方の村々まで行けばともかく、街中で生きている豚を見かけること自体がほとんどなくなってしまいました。
ということもあり、ザビーヤチカはスロバキア国内で少しずつ「伝説」になりかけています。私がザビーヤチカを体験してきたことに、首都ブラチスラバの知人達は少しびっくりしたわけです。
ところで、首都ブラチスラバからドナウ川沿いを車で15分ほど遡ったところに、デヴィーン城という美しい古城が聳えています。ここはドナウ川とモラヴァ川が分岐するところにあり、古代より交通の要衝とされてきました。古くはケルト人が居住し、ローマ帝国時代には帝国北の境界として城塞が作られました。その後歴史の変遷を経る中で数多くの王国や勢力の居城となりましたが、19世紀にナポレオンの攻撃を受けて攻め落とされました。
城は二つの川を見下ろす高い山頂に建てられており、上に登って睥睨すれば、二つの川の向こうに広がる広大な森、森、そして森が遠くまで延々と見渡せます。ドナウ川の向こうはオーストリア領、モラヴァ川を遡ればチェコ領です。ここから中央ヨーロッパが一望できるのではないか、という錯覚に陥るほどの素晴らしさです。
このお城があるデヴィーン村はブラチスラバ市から近く、自然が豊かで静か、落ち着いています。そのことから、仕事を引退したシニアな方々が好んで住むところだとも言われています。私はそこに住むスロバキア人の一家族に招待されて、10月のとある週末に、彼らが自宅の庭で開催したザビーヤチカ・パーティーに参加したのでした。
かわいい豚がブウブウ鳴いているところを、グサッと一突きして豚を「落とす」ところからザビーヤチカが始まる・・・のではないかと私は心配し、ある意味で覚悟して知人の自宅に向かいました。
しかし幸いなことに(?)、豚は前日に落とされ、電気鋸で真二つに縦に割られて、いわば一頭の半分だけが庭につるされていました。ちなみに雑学ですが、この半分に割られた豚の半身を、日本の食肉業界の専門用語で「半丸」と言うそうです。
ザビーヤチカは知人の家族と我々を含め全部で10人弱とアット・ホームな集まりでした。昔であれば一家の主人が自ら豚をさばいたのでしょうが、今では専門の職人さんがやってきて、みんなの見ている前で半丸をあれよあれよという間に見事にさばいていきます。それを見ている皆は、スリヴォヴィツァというスモモから作った強烈なスピリッツ(蒸留酒)や、ワインやビールを飲みながら、ワイワイとおしゃべりしたり、職人さんにちょっかいを出したりして楽しみます。私を招いてくれた一家の御主人の知人によると、昔からザビーヤチカは単に豚を解体して保存食を作るためだけではなく、家族や親族の大事な集まりの機会であり、お祭りであり、さらに言えば、昼間から堂々とお酒を飲める絶好の機会、ということなのでした。
私は自家用車を運転して来てしまったので、残念ながらお酒ではなくご家族が用意してくれた自家製レモネードを頂きながらの参加となりましたが、なにより感心したのは、職人さんが小さなナイフ一本で、50キロ近くある巨大な骨付きの半丸を手際よく、見事に捌いていくことです。これを見て思い出したのは、昔読んだ中国の古典「荘子 養生主篇」という本に書かれていた話でした。
「荘子」の記によると、古代中国に文恵君という王様がおり、彼に仕える「包丁」という名前の料理人がいました。包丁さんは、豚や牛など動物の、体の構造や骨、筋、肉の位置などに精通した、いわば「ザビーヤチカ」の名人でした。彼が豚の体を捌く時は、彼の指に導かれるナイフの先が「骨と骨の間のあるべきところに入っていき、筋と筋の間の切るべきところを切っていく」ので、彼が指に殆ど力を入れなくても、あっという間に一匹の豚が見事に解体されたということです。
この話は伝説とも言われていますが、その名残なのか、今でも日本語では料理用ナイフのことを「包丁」と呼びます。
さて、そんなことを考えている内に、現代スロバキアの「包丁さん」たる職人によって、半丸はすべての部位に解体されてしまいました。庭の机の上に並べられた様々な肉の塊の中で、白く大きく目立つのはやはり脂肪です。更に赤身の肉では、ロース、肩ロース、バラ、腿、腕等々。印象的だったのは、一番貴重で高価といわれるヒレ肉が、巨大な半丸の中からわずか600グラムしか取れないということでした。
本来であれば、これから参加者が総出でこれらの肉を加工し、ソーセージやハム、ベーコンなどを作らなければなりません。しかし今回ザビーヤチカを主催した家族は農家ではなくバイオリニストの音楽家御一家ということもあり、肉の加工は職人さんにお願いすることにして、ヒレ肉などごく一部だけを夫人に料理していただき、みんなで食べることとなりました。
なお、私が昔、東南アジアに在勤していた際に、地元の人々が主催する大きな宴会で、子豚の丸焼きを頂くことが度々ありました。その際には常に、子豚の耳と尻尾の部分が最高の御馳走とされ、皆で食べる前に、まず、その宴会に参加しているもっとも上席の人(概して一番の年長者)に、この二種類が切り取られ、差し出された、のを覚えています。
そんな記憶もあったことから、今回のザビーヤチカでもまわりのスロバキア人達に、「耳と尻尾はどうするの?どうやって食べるの?」と聞いてみました。が、彼らの答えはあっさりと、「誰も食べないよ。犬の餌にするぐらいかな」とのことでした。豚は世界各地で様々な調理法により食べられていますが、お国柄によって食べ方はずいぶん違うものだな、と思った次第です。
最後に、実は私は今から30年以上前にフランスに留学していた際に、ザビーヤチカを一度経験したことがあります。当時、フランス中部の山岳地帯(マッシブ・サントラル)にある山奥のフランス人の知人の農家を訪れ、年末年始を過ごす機会がありました。
そこでは生きている巨大な豚を大人が数人がかりで押さえつけ、首にナイフを突き立て、しぼり出てくる血をバケツに取るところからお祭りが始まりました。血はフランス語でブーダンという赤いソーセージを作るために使います。その後、農家の主人が自ら豚を解体し、家族総出で肉をハムやソーセージ、ベーコンやパテなどにしました。
私は初心者でなにもわかりませんでしたし、目の前で豚が落とされるのを見てなんともいえない気分だったので、彼らの作業をただ茫然と見ていました。しかし、一家の御主人から、お前も今日は我々家族の一員なんだからなにか手伝え、と言われました。そんなわけでむりやり、切り取られた巨大な豚の鼻を持たされて、古くなった歯ブラシでその二つの穴の中を掃除したのを今でも覚えています。
30年ぶりのザビーヤチカでしたが、改めて思ったことは、スロバキア人と同じく我々日本人も日常生活の中で毎日のように豚肉や牛肉、鶏肉を食べていながら、それをいただいている元となっている生き物たちの命には無頓着になっているということです。
日本人の多くは、魚の活け造り(生きたまま、あるいは落としたての魚を生のまま料理して食べる一品)には舌なめずりしても、落とされた豚や牛の顔を見たら卒倒しそうになってしまうのではないでしょうか。
豚を落とす、というと、目を背けたくなるように感じる日本人の方がいるかもしれませんが、けっしてそうは思いません。ザビーヤチカとはむしろ食べ物に感謝する、食べ物をいただいている元となっている命に感謝する、というセレモニーのように、私は感じとりました。わざわざザビーヤチカを主催し、私を招待してくれたスロバキア人の知人御一家に改めて感謝する次第です。
スロバキアはすっかり冬の風情で、朝晩は気温が氷点下近く下がる日もでてきました。日がどんどん短くなっていく中で、先月末には時計が夏時間から冬時間に切り替わりました。時には木枯らしも吹く寒い冬の毎日を過ごしながら、スロバキアの人々は少しずつ足音を立ててやってくるクリスマスの季節を待ち望みます。
文責 日本大使 新美 潤(しんみ じゅん)
「ザビーヤチカ」とはスロバキア語の「殺す(ザビッチ)」という単語に語源があります。スロバキアの村の農家の伝統的行事で、秋から冬に向かうちょうど今頃、自宅で飼っている豚を一匹落として(殺して)解体し、主として自家用の、ハムやベーコン、ソーセージなどの保存食を作る家族の「お祭り」です。
農家にとって豚は大事な売り物でもあり、財産です。それを冬を前に一匹「落として」しまうのは、昔は冬になると食料も乏しくなり、また暖房施設も今のようにないので、家族一同、栄養豊富でカロリーも高い豚肉を保存食として作り、それを食べて、いわば体の中から温めて寒い冬を乗りきる必要があったから、と言われています。更に、牧草や藁を食べて育つ牛や羊と異なり、豚は穀物や芋といった人間と同じような食べ物をとって大きくなるので、ただでさえ食料が乏しくなる冬の間は、食い扶持(食いブタ?)を少しでも減らしてその豚自身を食べてしまおう、という思惑もあったのではないか、とも思われます。
1993年のチェコスロバキアからのスロバキアの分離・独立、更にはその後の急速な経済発展により、スロバキア人は相対的に豊かになりました。スーパーマーケットには年中食べ物があふれ、建物には電気、ガス等の暖房設備が整備されるようになりました。そんな中で、スロバキア人の多くにとって、わざわざ冬前にザビーヤチカで豚を落として保存食を作る必要性はなくなってしまいました。また、スロバキア経済に占める農業生産の割合が3.74%(2014年統計)に減少する中、地方の村々まで行けばともかく、街中で生きている豚を見かけること自体がほとんどなくなってしまいました。
ということもあり、ザビーヤチカはスロバキア国内で少しずつ「伝説」になりかけています。私がザビーヤチカを体験してきたことに、首都ブラチスラバの知人達は少しびっくりしたわけです。
ところで、首都ブラチスラバからドナウ川沿いを車で15分ほど遡ったところに、デヴィーン城という美しい古城が聳えています。ここはドナウ川とモラヴァ川が分岐するところにあり、古代より交通の要衝とされてきました。古くはケルト人が居住し、ローマ帝国時代には帝国北の境界として城塞が作られました。その後歴史の変遷を経る中で数多くの王国や勢力の居城となりましたが、19世紀にナポレオンの攻撃を受けて攻め落とされました。
城は二つの川を見下ろす高い山頂に建てられており、上に登って睥睨すれば、二つの川の向こうに広がる広大な森、森、そして森が遠くまで延々と見渡せます。ドナウ川の向こうはオーストリア領、モラヴァ川を遡ればチェコ領です。ここから中央ヨーロッパが一望できるのではないか、という錯覚に陥るほどの素晴らしさです。
このお城があるデヴィーン村はブラチスラバ市から近く、自然が豊かで静か、落ち着いています。そのことから、仕事を引退したシニアな方々が好んで住むところだとも言われています。私はそこに住むスロバキア人の一家族に招待されて、10月のとある週末に、彼らが自宅の庭で開催したザビーヤチカ・パーティーに参加したのでした。
かわいい豚がブウブウ鳴いているところを、グサッと一突きして豚を「落とす」ところからザビーヤチカが始まる・・・のではないかと私は心配し、ある意味で覚悟して知人の自宅に向かいました。
しかし幸いなことに(?)、豚は前日に落とされ、電気鋸で真二つに縦に割られて、いわば一頭の半分だけが庭につるされていました。ちなみに雑学ですが、この半分に割られた豚の半身を、日本の食肉業界の専門用語で「半丸」と言うそうです。
ザビーヤチカは知人の家族と我々を含め全部で10人弱とアット・ホームな集まりでした。昔であれば一家の主人が自ら豚をさばいたのでしょうが、今では専門の職人さんがやってきて、みんなの見ている前で半丸をあれよあれよという間に見事にさばいていきます。それを見ている皆は、スリヴォヴィツァというスモモから作った強烈なスピリッツ(蒸留酒)や、ワインやビールを飲みながら、ワイワイとおしゃべりしたり、職人さんにちょっかいを出したりして楽しみます。私を招いてくれた一家の御主人の知人によると、昔からザビーヤチカは単に豚を解体して保存食を作るためだけではなく、家族や親族の大事な集まりの機会であり、お祭りであり、さらに言えば、昼間から堂々とお酒を飲める絶好の機会、ということなのでした。
私は自家用車を運転して来てしまったので、残念ながらお酒ではなくご家族が用意してくれた自家製レモネードを頂きながらの参加となりましたが、なにより感心したのは、職人さんが小さなナイフ一本で、50キロ近くある巨大な骨付きの半丸を手際よく、見事に捌いていくことです。これを見て思い出したのは、昔読んだ中国の古典「荘子 養生主篇」という本に書かれていた話でした。
「荘子」の記によると、古代中国に文恵君という王様がおり、彼に仕える「包丁」という名前の料理人がいました。包丁さんは、豚や牛など動物の、体の構造や骨、筋、肉の位置などに精通した、いわば「ザビーヤチカ」の名人でした。彼が豚の体を捌く時は、彼の指に導かれるナイフの先が「骨と骨の間のあるべきところに入っていき、筋と筋の間の切るべきところを切っていく」ので、彼が指に殆ど力を入れなくても、あっという間に一匹の豚が見事に解体されたということです。
この話は伝説とも言われていますが、その名残なのか、今でも日本語では料理用ナイフのことを「包丁」と呼びます。
さて、そんなことを考えている内に、現代スロバキアの「包丁さん」たる職人によって、半丸はすべての部位に解体されてしまいました。庭の机の上に並べられた様々な肉の塊の中で、白く大きく目立つのはやはり脂肪です。更に赤身の肉では、ロース、肩ロース、バラ、腿、腕等々。印象的だったのは、一番貴重で高価といわれるヒレ肉が、巨大な半丸の中からわずか600グラムしか取れないということでした。
本来であれば、これから参加者が総出でこれらの肉を加工し、ソーセージやハム、ベーコンなどを作らなければなりません。しかし今回ザビーヤチカを主催した家族は農家ではなくバイオリニストの音楽家御一家ということもあり、肉の加工は職人さんにお願いすることにして、ヒレ肉などごく一部だけを夫人に料理していただき、みんなで食べることとなりました。
なお、私が昔、東南アジアに在勤していた際に、地元の人々が主催する大きな宴会で、子豚の丸焼きを頂くことが度々ありました。その際には常に、子豚の耳と尻尾の部分が最高の御馳走とされ、皆で食べる前に、まず、その宴会に参加しているもっとも上席の人(概して一番の年長者)に、この二種類が切り取られ、差し出された、のを覚えています。
そんな記憶もあったことから、今回のザビーヤチカでもまわりのスロバキア人達に、「耳と尻尾はどうするの?どうやって食べるの?」と聞いてみました。が、彼らの答えはあっさりと、「誰も食べないよ。犬の餌にするぐらいかな」とのことでした。豚は世界各地で様々な調理法により食べられていますが、お国柄によって食べ方はずいぶん違うものだな、と思った次第です。
最後に、実は私は今から30年以上前にフランスに留学していた際に、ザビーヤチカを一度経験したことがあります。当時、フランス中部の山岳地帯(マッシブ・サントラル)にある山奥のフランス人の知人の農家を訪れ、年末年始を過ごす機会がありました。
そこでは生きている巨大な豚を大人が数人がかりで押さえつけ、首にナイフを突き立て、しぼり出てくる血をバケツに取るところからお祭りが始まりました。血はフランス語でブーダンという赤いソーセージを作るために使います。その後、農家の主人が自ら豚を解体し、家族総出で肉をハムやソーセージ、ベーコンやパテなどにしました。
私は初心者でなにもわかりませんでしたし、目の前で豚が落とされるのを見てなんともいえない気分だったので、彼らの作業をただ茫然と見ていました。しかし、一家の御主人から、お前も今日は我々家族の一員なんだからなにか手伝え、と言われました。そんなわけでむりやり、切り取られた巨大な豚の鼻を持たされて、古くなった歯ブラシでその二つの穴の中を掃除したのを今でも覚えています。
30年ぶりのザビーヤチカでしたが、改めて思ったことは、スロバキア人と同じく我々日本人も日常生活の中で毎日のように豚肉や牛肉、鶏肉を食べていながら、それをいただいている元となっている生き物たちの命には無頓着になっているということです。
日本人の多くは、魚の活け造り(生きたまま、あるいは落としたての魚を生のまま料理して食べる一品)には舌なめずりしても、落とされた豚や牛の顔を見たら卒倒しそうになってしまうのではないでしょうか。
豚を落とす、というと、目を背けたくなるように感じる日本人の方がいるかもしれませんが、けっしてそうは思いません。ザビーヤチカとはむしろ食べ物に感謝する、食べ物をいただいている元となっている命に感謝する、というセレモニーのように、私は感じとりました。わざわざザビーヤチカを主催し、私を招待してくれたスロバキア人の知人御一家に改めて感謝する次第です。
スロバキアはすっかり冬の風情で、朝晩は気温が氷点下近く下がる日もでてきました。日がどんどん短くなっていく中で、先月末には時計が夏時間から冬時間に切り替わりました。時には木枯らしも吹く寒い冬の毎日を過ごしながら、スロバキアの人々は少しずつ足音を立ててやってくるクリスマスの季節を待ち望みます。
文責 日本大使 新美 潤(しんみ じゅん)