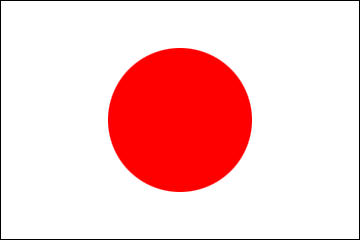二十四節気ごはん12月
令和2年12月8日
12月は二十四節気では、大雪(雪が本格的に降り始める)と冬至(大雪が降り始め冬魚の漁が盛んになる、夜が最も長くなる)で、年の瀬です。
今回は、年の瀬の風習をいくつかご紹介します。
銭湯ができた江戸時代より、「冬至にゆず湯に入ると風邪を引かない」と言われています。「冬至」は「湯治(とうじ)」、「ゆず」は「融通(ゆうずう)」という語呂合わせから、「お風呂に入って融通よく生きましょう」という意味があるそうです。今でも、冬至になると全国各地の温泉や各家庭で多くの人々がゆず湯を愉しみます。
また、年の瀬には煤(すす)払いが恒例です。年始に各家庭を訪れる歳神様(田の神様)は清浄な空間を好んで汚い家には入りたがらないため、人々は旧年の汚れを清めて歳神様を迎え入れました。これが今日まで伝えられ、煤汚れとは無縁の生活となった現在でも、年の瀬には各家庭で大掃除、神社やお寺では煤払い行事が行われています。
そして、寺院では年末年始の深夜0時を挟む時間帯に鐘を108回撞きます。これを除夜の鐘と言います。仏教では、人には108の煩悩があるとされ、その煩悩を祓うために同じ回数だけ鐘を撞きます。煩悩とは、人の心を惑わせたり、悩ませ苦しめたりする心のはたらきのことを言います。
12月は旧年を終え、新年を迎えるために慌ただしくなる時期です。そんな時期に健康と幸せを願って食べられるお料理として、かぼちゃ煮、鶏団子の根菜汁、銀杏の炊込飯と年越しそばをご紹介します。
今回は、年の瀬の風習をいくつかご紹介します。
銭湯ができた江戸時代より、「冬至にゆず湯に入ると風邪を引かない」と言われています。「冬至」は「湯治(とうじ)」、「ゆず」は「融通(ゆうずう)」という語呂合わせから、「お風呂に入って融通よく生きましょう」という意味があるそうです。今でも、冬至になると全国各地の温泉や各家庭で多くの人々がゆず湯を愉しみます。
また、年の瀬には煤(すす)払いが恒例です。年始に各家庭を訪れる歳神様(田の神様)は清浄な空間を好んで汚い家には入りたがらないため、人々は旧年の汚れを清めて歳神様を迎え入れました。これが今日まで伝えられ、煤汚れとは無縁の生活となった現在でも、年の瀬には各家庭で大掃除、神社やお寺では煤払い行事が行われています。
そして、寺院では年末年始の深夜0時を挟む時間帯に鐘を108回撞きます。これを除夜の鐘と言います。仏教では、人には108の煩悩があるとされ、その煩悩を祓うために同じ回数だけ鐘を撞きます。煩悩とは、人の心を惑わせたり、悩ませ苦しめたりする心のはたらきのことを言います。
12月は旧年を終え、新年を迎えるために慌ただしくなる時期です。そんな時期に健康と幸せを願って食べられるお料理として、かぼちゃ煮、鶏団子の根菜汁、銀杏の炊込飯と年越しそばをご紹介します。
 © Izu Shaboten Zoo Group |
 © HIROSHI MIZOBUCHI/SEBUN © HIROSHI MIZOBUCHI/SEBUN PHOTO/amanaimages |
 © FUMIHIKO MURAKAMI/SEBUNPHOTO/amanaimages |
| ゆず湯 温泉を愉しむカピバラ(伊豆シャボテン動物公園) |
寺での煤払い |
除夜の鐘を撞く様子 |
 |
 かぼちゃ煮 |
| 古来、黄色は魔除けの色とされていました。 かぼちゃは栄養価も高く、1年の区切りであ る冬至に食べることで無病息災を祈りました。 また、名前に「ん」のつく食材を食べると幸運 に繋がるという説もあります。かぼちゃは南瓜 (なんきん)ともいい、「ん」が名前に入ってい ます。 |
|
 鶏団子の根菜汁、銀杏の炊込飯 |
 海老と茸の天ぷらの年越し蕎麦
|
| その他「ん」のつく食材(蓮根、大根、人参、 銀杏など)を食べると運を呼び込めると言わ れています。 |
12月31日の夜の年越し前に蕎麦を食べることは 日本の風物詩です。そばは他の麺類よりも切れ やすいことから、「旧年1年の災厄を断ち切る」と いう意味があります。また、海老は腰が曲がって いる姿から、長寿の象徴でもあります。 |