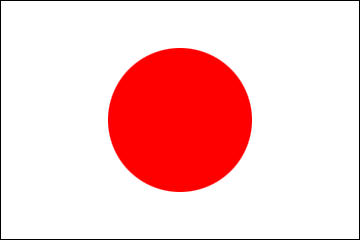二十四節気ごはん1月
1月は二十四節気では、小寒(寒さが厳しくなる)、大寒(1年で最も寒さが厳しくなり、武道では寒稽古が行われる)で、1年のうちで寒さが最も厳しくなる季節であるとともに、新年のおめでたい月でもあります。
今回は、日本での新年の伝統や過ごし方についてご紹介します。
日本では新年行事を行う期間を「お正月」といいます。そのうち「正月三が日」とは1月1日~3日の三日間で国民の祝日となっています。日本人にとってお正月は、欧米でのクリスマスのように家族と祝い一緒に過ごす最も大切な年中行事です。
12月記事でも触れましたが、正月には「歳神様」と呼ばれる幸運の神様が各家庭にやってきます。神様を迎え入れるために、家の玄関に門松、注連縄(しめなわ)飾りや鏡餅を飾ります。
年が明けると、まずは神社に参拝して、新しい一年を迎える感謝と新年の無事と平安を祈ります。これを初詣といい、年明けすぐの深夜から1月7日までの間に参拝するのが一般的です。この期間は、神社にはたくさんの屋台が出て多くの人々で賑わいます。
欧米ではクリスマスカードを送り合うように、日本ではお正月に年賀状というハガキを友人や親戚等に送り、新年の挨拶をします。また、お正月の面白い風習の一つにお年玉があります。小さな封筒に入れたお金を親から子供、年長者から年少者へ、目上から目下へ贈る風習です。子供たちにとっては、親や親戚からお年玉をもらえるので、お正月の一番楽しみなイベントです。
このように、お正月は家族や親戚が集まり、新年をみんなで祝いのんびりと過ごします。そんなお正月に食べる特別な料理として、おせち料理とお雑煮をご紹介します(詳細説明は写真をご覧下さい)。
 |
 |
 |
| © JAPACK/a.collectionRF/amanaimages 門松 門松は歳神様が迷わずに家を見つけるため の目印として家の玄関前に飾る物です。 |
© yonehara keitaro/a.collectionRF/amanaimages 注連縄(しめなわ)飾り 歳神様を迎える準備ができていて清められた場 所であることを表す飾りです。 |
© yonehara keitaro /a.collectionRF/amanaimages |
 |
 |
 |
|
© HIROSHI MIZOBUCHI/SEBUN PHOTO/amanaimages 初詣の様子(住吉大社) |
おせち料理 おせち料理には20~30種類あり、それぞれの 料理には意味が込められています。おせち料 理は歳神様へのお供え物であり、正月三が日 は歳神様とおせち料理を食べてのんびり過ごし ます。お正月は家事をしなくても良いように、保 存のきく料理になっています。 |
数あるおせち料理の中から面白い意味の 料理をいくつか紹介します。 伊達巻(左上):形が巻物に似ているため学業成就 数の子(真ん中上):子宝に恵まれる 黒豆(右真ん中):「豆に働く」=真面目 栗金団(真ん中下):金の団子で豊かな一年 田作り(右下):昔はイワシを田の肥料に 使っていたため,五穀豊穣 |
 |
 |
 |
| ブリ照焼(右真ん中): 日本ではブリは成長に応じて名前が変わり ます。武士も元服や出世に伴って名前を変 えたため,出世祈願の意味があります。 菊花蕪(きっかかぶ)(右下): カブを菊に見立てて切り,酢の物にしたも の。菊には邪気払いと不老長寿の意味が あります。 |
お煮しめ 様々な食材を一緒に鍋で煮ることから、 家族が仲良く、末長く繁栄するようにと の願いが込められています。 |
お雑煮 大晦日の夜に、海や山の幸を神様にお供え |