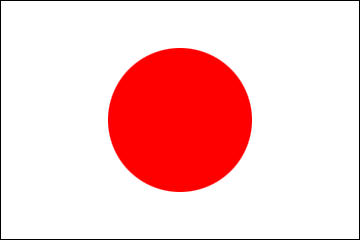二十四節気ごはん4月
令和3年4月8日
4月は二十四節気では、晴明(万物がきらきらと汚れなく輝く)、穀雨(春の雨の降る時期で、農作物がよく育つ)で、日の光と春雨によって穀物はすくすくと成長し、日ごとに木々の緑は鮮やかになっていく時期です。
皆さんもご存知のように、4月は日本では桜が咲き誇る季節であり、多くの日本人が待ち侘びるお花見の季節です。この季節になると、日本の天気予報は「桜前線」の予報も流して、どの街でいつ頃桜が咲き始めるのか予想を始めます。一つの花の開花状況を全国でニュースにするのは世界のなかでも日本の桜だけでしょう。それくらい日本人にとって桜は特別な花です。今回の記事では、日本のお花見の歴史などをご紹介します。
日本でお花見といえば元々は大陸から伝わった梅の花を愛でることでしたが、平安時代から桜の花を愛でるようになりました。日本で最初に桜の花見を始めたのは嵯峨天皇と言われており、9世紀のことです。その後長い間、花見は天皇、貴族、あるいは権力を握った武家だけの楽しみでした。天下を統一した豊臣秀吉(16世紀)の豪勢な花見は今も歴史に伝わります。
江戸時代(17世紀から19世紀)になり戦乱のない安定した世になって初めて、花見は庶民の楽しみともなりました。弁当を作り衣装を新調して、庶民も花見に出かけるようになりました。現代でも花見の名所と言われるところは、その頃の君主が庶民のために人工的に作ったものが多いです。東京なら上野公園、墨田川の堰堤(墨堤)、飛鳥山。すべて江戸時代に整備された桜の名所です。
日本人がこれほどに桜を愛するのは、樹木全体に満開に咲きそろった桜の花が、短期間のあいだに一斉に潔く散っていく風情が日本人の美学に合っているからだと言われています。平安時代から現代にいたるまで、桜を詠んだ和歌などの文学作品、桜を舞台に繰り広げられる能や歌舞伎などの古典芸能が数多くあり、その学問的意味についても多数の研究が行われています。桜の美しさ、その潔く散る姿が日本人の人生観、死生観に訴えるものを持っているからだと考えられています。
昨年は、日本・スロバキア交流100周年を記念して、スロバキアの各地に桜を植樹するプロジェクトを展開いたしました(植樹場所などについては日本大使館のHPをご参照ください。ブルーミング・スロバキア・キャンペーン | 在スロバキア日本国大使館 (https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000869.html))。これまでにスロバキアの各地に植えられた450本の桜が、これからも末永く、スロバキアの皆さんに愛され、スロバキアでの春の時期の楽しみとして咲き続けることを心から願っています。
お花見とお供といえば、花見団子と花見弁当です。どちらも江戸時代にお花見の宴会が大衆化された頃から、お花見のお供として定番となりました。今回は花見団子と花見弁当の他に,春の代表的な和菓子である桜餅も石森料理人にご用意頂きました。それぞれの説明は写真からご覧ください。花見弁当の筍ごはんの作り方は動画でもご紹介をしていますので,そちらもぜひご視聴さい。
皆さんもご存知のように、4月は日本では桜が咲き誇る季節であり、多くの日本人が待ち侘びるお花見の季節です。この季節になると、日本の天気予報は「桜前線」の予報も流して、どの街でいつ頃桜が咲き始めるのか予想を始めます。一つの花の開花状況を全国でニュースにするのは世界のなかでも日本の桜だけでしょう。それくらい日本人にとって桜は特別な花です。今回の記事では、日本のお花見の歴史などをご紹介します。
日本でお花見といえば元々は大陸から伝わった梅の花を愛でることでしたが、平安時代から桜の花を愛でるようになりました。日本で最初に桜の花見を始めたのは嵯峨天皇と言われており、9世紀のことです。その後長い間、花見は天皇、貴族、あるいは権力を握った武家だけの楽しみでした。天下を統一した豊臣秀吉(16世紀)の豪勢な花見は今も歴史に伝わります。
江戸時代(17世紀から19世紀)になり戦乱のない安定した世になって初めて、花見は庶民の楽しみともなりました。弁当を作り衣装を新調して、庶民も花見に出かけるようになりました。現代でも花見の名所と言われるところは、その頃の君主が庶民のために人工的に作ったものが多いです。東京なら上野公園、墨田川の堰堤(墨堤)、飛鳥山。すべて江戸時代に整備された桜の名所です。
日本人がこれほどに桜を愛するのは、樹木全体に満開に咲きそろった桜の花が、短期間のあいだに一斉に潔く散っていく風情が日本人の美学に合っているからだと言われています。平安時代から現代にいたるまで、桜を詠んだ和歌などの文学作品、桜を舞台に繰り広げられる能や歌舞伎などの古典芸能が数多くあり、その学問的意味についても多数の研究が行われています。桜の美しさ、その潔く散る姿が日本人の人生観、死生観に訴えるものを持っているからだと考えられています。
昨年は、日本・スロバキア交流100周年を記念して、スロバキアの各地に桜を植樹するプロジェクトを展開いたしました(植樹場所などについては日本大使館のHPをご参照ください。ブルーミング・スロバキア・キャンペーン | 在スロバキア日本国大使館 (https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000869.html))。これまでにスロバキアの各地に植えられた450本の桜が、これからも末永く、スロバキアの皆さんに愛され、スロバキアでの春の時期の楽しみとして咲き続けることを心から願っています。
お花見とお供といえば、花見団子と花見弁当です。どちらも江戸時代にお花見の宴会が大衆化された頃から、お花見のお供として定番となりました。今回は花見団子と花見弁当の他に,春の代表的な和菓子である桜餅も石森料理人にご用意頂きました。それぞれの説明は写真からご覧ください。花見弁当の筍ごはんの作り方は動画でもご紹介をしていますので,そちらもぜひご視聴さい。
 |
 |
| 飛鳥山花見(作者:歌川広重) 江戸時代の花見の様子 画像出典:東京国立博物館研究情報アーカイブス (https://webarchives.tnm.jp/) |
東京墨田川(墨堤:ぼくてい)の桜 |
 |
 |
| 岡山県の醍醐桜 |
|
 |
 |
| 筍ごはん 筍の旬は先春で、この時期の筍は新鮮で風味 も豊かなことから、代表的な春の味覚です。 |
花見団子と桜餅 花見には和菓子が欠かせません。花見団子の 白は雪の名残、ピンクは桜の花、緑は夏の兆 しを表していると言われています。また、桜 の葉で包んだ桜餅も花見菓子の定番です。 |