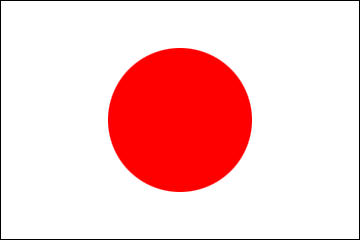二十四節気ごはん6月
令和3年6月30日
二十四節気では、6月は芒種(穀物の種をまく)と夏至(昼が最も長い頃であり、梅雨の最中)です。6月は水無月(みなづき)(漢字では「水が無い月」と書きますが、意味は「水の月」)といわれ、日本では雨が多くなる季節に入ります。同時に、色鮮やかな美しい紫陽花が各所で咲き、人々の目を楽しませます。
日本の雨季は、現在は「梅」と「雨」という漢字2文字を使い、「梅雨」(つゆ)と呼ばれます。その表記の由来については、梅の実が熟す時期に降る雨だからなど様々な説がありますが正確なところはわかりません。梅雨の雨は米作りにとって不可欠のものです。昔は梅雨の雨を利用して水田を作り田植えをしていましたが、現在では稲の品種改良などの努力もあり、田植えは6月より前に行われることが一般となっています。日本人の梅雨の過ごし方は変化していますが、季節のなかで重要な節目であることは変わりません。現在でも、天気予報では日本の地域ごとに「梅雨入り」した日を知らせており、季節の移り変わりを感じさせます。
また、今日6月30日には、「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」という日本古来の行事が各地の神社で行われます。これは新年を迎えてから半年間を無事に過ごせたことに感謝するとともに、その半年間に心身についた穢れを祓い清め、残り半年間を清らかな気持ちで過ごせるよう願う神事です。その起源は神話の世界にまで遡り、8世紀には正式な宮中行事として位置づけられた重要な年中行事です。「大祓」は夏と年末の2回行われ、夏のものを「夏越の大祓」、年末のものを「年越の大祓」と呼びます。
夏越の大祓に合わせて、各地の神社では参拝者が「茅の輪くぐり」をして心身を清め今後の健康を祈るのが人気です。写真にもあるような大きな茅の輪を左回りに右回りにと3回くぐり抜けてから拝殿での祈祷に進みます。日本人は昔から季節の節目に「穢れを祓うこと」をとても大切にしており、この「茅の輪くぐり」も日本人にとっては心・精神の定期的な大掃除ともいえるかもしれません。
この「夏越の大祓」が行われる6月30日には、涼しげな和菓子の「水無月」を食べるのが人気です。また、6月が旬であるタコを使った料理2種をご紹介します。それぞれのお料理については写真にて説明していますので、ご覧下さい。

茅の輪くぐり
茅の輪くぐりも神話に起源があります。「古事記」「日本書紀」に力の象徴として登場する「スサノオノミコト」に一晩の宿を提供した者がその御礼に受け取った「茅の輪」のおかげで、その後の疫病を避けることができたという神話です。人類が疫病に悩まされる現在、「茅の輪くぐり」で疫病退散を念じたいものです。

日本の夏はとても蒸し暑く、体調を崩したり、食欲がなくなってしまう人も多くいます。このように、栄養価が高く涼しげな料理を食べることで、厳しい夏を乗り越えます。

水無月(和菓子)
水無月という和菓子は、無病息災を祈って6月30日に食べられる京都のお菓子でしたが、現在では各地でも人気です。平安時代には氷室から氷を切り出して食べ、暑気払いをする宮中の風習がありました。当時の庶民にとって氷は手の届かないものだったので、氷の代わりに、氷を表現した三角形のお菓子を食べたのが始まりと言われています。上にのる小豆の赤い色は魔除けのためとも言われています。

タコと夏野菜の冷製煮物
日本各地の夏至の風習はたくさんあります。一部の地域(関西)では、豊作祈願や夏バテ防止から、6月に旬であるタコを使った料理を食べます。

タコの湯引き 土佐酢ジュレ
日本の雨季は、現在は「梅」と「雨」という漢字2文字を使い、「梅雨」(つゆ)と呼ばれます。その表記の由来については、梅の実が熟す時期に降る雨だからなど様々な説がありますが正確なところはわかりません。梅雨の雨は米作りにとって不可欠のものです。昔は梅雨の雨を利用して水田を作り田植えをしていましたが、現在では稲の品種改良などの努力もあり、田植えは6月より前に行われることが一般となっています。日本人の梅雨の過ごし方は変化していますが、季節のなかで重要な節目であることは変わりません。現在でも、天気予報では日本の地域ごとに「梅雨入り」した日を知らせており、季節の移り変わりを感じさせます。
また、今日6月30日には、「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」という日本古来の行事が各地の神社で行われます。これは新年を迎えてから半年間を無事に過ごせたことに感謝するとともに、その半年間に心身についた穢れを祓い清め、残り半年間を清らかな気持ちで過ごせるよう願う神事です。その起源は神話の世界にまで遡り、8世紀には正式な宮中行事として位置づけられた重要な年中行事です。「大祓」は夏と年末の2回行われ、夏のものを「夏越の大祓」、年末のものを「年越の大祓」と呼びます。
夏越の大祓に合わせて、各地の神社では参拝者が「茅の輪くぐり」をして心身を清め今後の健康を祈るのが人気です。写真にもあるような大きな茅の輪を左回りに右回りにと3回くぐり抜けてから拝殿での祈祷に進みます。日本人は昔から季節の節目に「穢れを祓うこと」をとても大切にしており、この「茅の輪くぐり」も日本人にとっては心・精神の定期的な大掃除ともいえるかもしれません。
この「夏越の大祓」が行われる6月30日には、涼しげな和菓子の「水無月」を食べるのが人気です。また、6月が旬であるタコを使った料理2種をご紹介します。それぞれのお料理については写真にて説明していますので、ご覧下さい。

茅の輪くぐり
茅の輪くぐりも神話に起源があります。「古事記」「日本書紀」に力の象徴として登場する「スサノオノミコト」に一晩の宿を提供した者がその御礼に受け取った「茅の輪」のおかげで、その後の疫病を避けることができたという神話です。人類が疫病に悩まされる現在、「茅の輪くぐり」で疫病退散を念じたいものです。

日本の夏はとても蒸し暑く、体調を崩したり、食欲がなくなってしまう人も多くいます。このように、栄養価が高く涼しげな料理を食べることで、厳しい夏を乗り越えます。

水無月(和菓子)
水無月という和菓子は、無病息災を祈って6月30日に食べられる京都のお菓子でしたが、現在では各地でも人気です。平安時代には氷室から氷を切り出して食べ、暑気払いをする宮中の風習がありました。当時の庶民にとって氷は手の届かないものだったので、氷の代わりに、氷を表現した三角形のお菓子を食べたのが始まりと言われています。上にのる小豆の赤い色は魔除けのためとも言われています。

タコと夏野菜の冷製煮物
日本各地の夏至の風習はたくさんあります。一部の地域(関西)では、豊作祈願や夏バテ防止から、6月に旬であるタコを使った料理を食べます。

タコの湯引き 土佐酢ジュレ