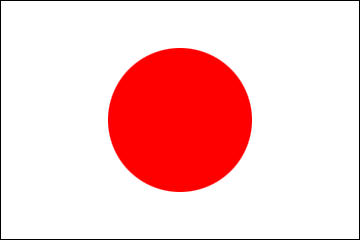二十四節気ごはん7月
令和3年7月7日
二十四節気では、7月は小暑(梅雨明けが近づき、暑さが本格的になる)と大暑(最も暑さが厳しくなる)で、梅雨が終わり、日本全国各地で夏祭りや花火大会が行われます。
日本には、季節の節目を意味する「五節句」という5つの節句があります。過去の記事でご紹介した3月3日「桃の節句」(ひな祭り)、5月5日「端午の節句」(こどもの日)も五節句に含まれます。今日、7月7日も五節句の一つで「七夕(たなばた)」と言います。七夕では、願い事を書いた短冊を笹の枝に結んで飾ります。こうした風習は、奈良時代に、7月7日の夜にだけ再会することを許された織姫と彦星の言い伝えとともに大陸から日本に入ってきたものです。
昔、大空をつかさどる天帝に仕える牛飼いの若者、牽牛(けんぎゅう)、と天帝のお后のために機織りをする娘、織女(しょくじょ)、が恋に落ちました。しかし、二人は恋に夢中になるあまり、次第に仕事を怠けるようになりました。そのことが天帝の怒りを買い、二人は天の川を挟んで離れ離れにされてしまい、年に一度、7月7日の夜だけ会うことを許されるようになったのです。現代の我々もこの二人を織姫(おりひめ)、彦星(ひこぼし)と呼んで親しみ、七夕の夜が雨になると、二人が会えるのだろうかと夜空に思いをはせるのです。
今月は、夏によく食べられる「鰻のひつまぶし」もご紹介します。鰻は、古くから日本人には栄養価の高い食べ物として知られ、8世紀の万葉集にも、夏痩せの友人に鰻を勧めるユニークな和歌が残されています。また、江戸時代には、夏に鰻を食べる宣伝が始められ、現代でも、特に7月には皆が鰻を食べに出かける習慣が定着しています。

笹には願い事を書いた短冊の他にも、折鶴や綱飾り等、いろいろな飾り物が飾られます。それぞれの飾りには意味があり、折鶴は長寿、綱飾りは大漁を願って飾られます。

地域によって諸説ありますが、7月7日に雨が降ると、天の川が氾濫して橋を渡れず、その年は彦星と織姫は会うことができないと言われています。また、晴れていると短冊に書いた願い事が空まで届いて願い事が叶うとも言われており、多くの人が七夕に晴れることを願っています。


七夕そうめん
平安時代の書物には、七夕にそうめんを食べると大病にかからないとの記載があり、古くから宮中では無病息災を願って七夕にそうめんが食べられていました。願い事をする短冊の5色(青(緑)、赤、黄、白、黒(紫))を表現したそうめんも食べられます。

鰻のひつまぶし
立秋前の18日間は「夏の土用」と呼ばれ、この時期は非常に日射しが強くなります。体調を崩す人も多く、江戸時代からこの時期に栄養価の高い鰻を食べる習慣が生まれました。「ひつまぶし」とは、御飯を入れておく容器である「おひつ」に白飯と鰻を詰めたことから名付けられました。

鰻のひつまぶしの食べ方をご紹介いたします。
1 おひつの鰻とご飯をお茶碗にいれて、そのまま鰻の味を楽しみます。
2 次は薬味(葱、海苔、香辛料、漬物等)をのせて、鰻との爽やかな風味を楽しみます。
3 さらに、薬味をのせた所に、出汁やお茶をかけて出汁茶漬け風に。
お茶漬けのさらさらした感覚に、鰻の風味が広がります。最後はお気に入りの食べ方で食べます。
日本には、季節の節目を意味する「五節句」という5つの節句があります。過去の記事でご紹介した3月3日「桃の節句」(ひな祭り)、5月5日「端午の節句」(こどもの日)も五節句に含まれます。今日、7月7日も五節句の一つで「七夕(たなばた)」と言います。七夕では、願い事を書いた短冊を笹の枝に結んで飾ります。こうした風習は、奈良時代に、7月7日の夜にだけ再会することを許された織姫と彦星の言い伝えとともに大陸から日本に入ってきたものです。
昔、大空をつかさどる天帝に仕える牛飼いの若者、牽牛(けんぎゅう)、と天帝のお后のために機織りをする娘、織女(しょくじょ)、が恋に落ちました。しかし、二人は恋に夢中になるあまり、次第に仕事を怠けるようになりました。そのことが天帝の怒りを買い、二人は天の川を挟んで離れ離れにされてしまい、年に一度、7月7日の夜だけ会うことを許されるようになったのです。現代の我々もこの二人を織姫(おりひめ)、彦星(ひこぼし)と呼んで親しみ、七夕の夜が雨になると、二人が会えるのだろうかと夜空に思いをはせるのです。
今月は、夏によく食べられる「鰻のひつまぶし」もご紹介します。鰻は、古くから日本人には栄養価の高い食べ物として知られ、8世紀の万葉集にも、夏痩せの友人に鰻を勧めるユニークな和歌が残されています。また、江戸時代には、夏に鰻を食べる宣伝が始められ、現代でも、特に7月には皆が鰻を食べに出かける習慣が定着しています。

笹には願い事を書いた短冊の他にも、折鶴や綱飾り等、いろいろな飾り物が飾られます。それぞれの飾りには意味があり、折鶴は長寿、綱飾りは大漁を願って飾られます。

地域によって諸説ありますが、7月7日に雨が降ると、天の川が氾濫して橋を渡れず、その年は彦星と織姫は会うことができないと言われています。また、晴れていると短冊に書いた願い事が空まで届いて願い事が叶うとも言われており、多くの人が七夕に晴れることを願っています。


七夕そうめん
平安時代の書物には、七夕にそうめんを食べると大病にかからないとの記載があり、古くから宮中では無病息災を願って七夕にそうめんが食べられていました。願い事をする短冊の5色(青(緑)、赤、黄、白、黒(紫))を表現したそうめんも食べられます。

鰻のひつまぶし
立秋前の18日間は「夏の土用」と呼ばれ、この時期は非常に日射しが強くなります。体調を崩す人も多く、江戸時代からこの時期に栄養価の高い鰻を食べる習慣が生まれました。「ひつまぶし」とは、御飯を入れておく容器である「おひつ」に白飯と鰻を詰めたことから名付けられました。

鰻のひつまぶしの食べ方をご紹介いたします。
1 おひつの鰻とご飯をお茶碗にいれて、そのまま鰻の味を楽しみます。
2 次は薬味(葱、海苔、香辛料、漬物等)をのせて、鰻との爽やかな風味を楽しみます。
3 さらに、薬味をのせた所に、出汁やお茶をかけて出汁茶漬け風に。
お茶漬けのさらさらした感覚に、鰻の風味が広がります。最後はお気に入りの食べ方で食べます。