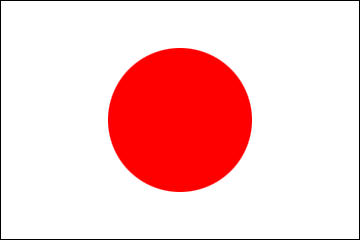二十四節季ごはん9月
令和3年9月20日
二十四節気では、9月は白露(空気が冷えて草木に露が降り始める)と秋分(昼と夜の長さが同じになる)で、日本では、暑すぎず寒すぎない秋は、春と並び愛されてきた美しい季節です。
9月には、「十五夜」や「お彼岸」といった年中行事があります。
十五夜は別名「お月見」とも呼ばれ、文字通り、美しい月を愛でる行事です。そもそも十五夜とは、旧暦8月15日(今年は9月21日にあたる)を意味します。そして、1年の中で最も空気が澄み渡る秋のちょうど真ん中の月は最も美しいとされ、「中秋の名月」とも呼ばれます。十五夜にお月見をする風習は平安時代(西暦800年代)に中国から日本に伝わり、貴族の間で広まりました。当時は、月を眺めながら宴会をして詩歌を作ったり、管弦を演奏したり楽しんでいましたが、十五夜の風習が庶民の間にも広まると、収穫祭の意味合いが強くなっていったそうです。十五夜の月は満月で、日本では、月にはうさぎがいてお餅をついている、と言われています。
また、9月には秋のお彼岸という行事もあります。秋分の日を中心とした前後1週間がお彼岸であり、今年は9月20日~9月26日にあたります。実は、春のお彼岸も存在し、春分の日を中心した前後1週間が春のお彼岸になります。この春と秋のお彼岸の時期には、家の仏壇を掃除したり、お墓参りやお供え物をして先祖を供養する風習があります。この風習も、やはり平安時代に起こったようですが、インドや中国にもない、日本のみで行われる年中行事です。春・秋のお彼岸、夏のお盆と年に3回あるわけで、先祖を敬い、思いを馳せることは、私たち日本人にとってとても大切なことなのです。
今回は、十五夜とお彼岸のお供え物として月見団子とおはぎの2品をご紹介します。それぞれの解説は写真からご覧ください。
9月には、「十五夜」や「お彼岸」といった年中行事があります。
十五夜は別名「お月見」とも呼ばれ、文字通り、美しい月を愛でる行事です。そもそも十五夜とは、旧暦8月15日(今年は9月21日にあたる)を意味します。そして、1年の中で最も空気が澄み渡る秋のちょうど真ん中の月は最も美しいとされ、「中秋の名月」とも呼ばれます。十五夜にお月見をする風習は平安時代(西暦800年代)に中国から日本に伝わり、貴族の間で広まりました。当時は、月を眺めながら宴会をして詩歌を作ったり、管弦を演奏したり楽しんでいましたが、十五夜の風習が庶民の間にも広まると、収穫祭の意味合いが強くなっていったそうです。十五夜の月は満月で、日本では、月にはうさぎがいてお餅をついている、と言われています。
また、9月には秋のお彼岸という行事もあります。秋分の日を中心とした前後1週間がお彼岸であり、今年は9月20日~9月26日にあたります。実は、春のお彼岸も存在し、春分の日を中心した前後1週間が春のお彼岸になります。この春と秋のお彼岸の時期には、家の仏壇を掃除したり、お墓参りやお供え物をして先祖を供養する風習があります。この風習も、やはり平安時代に起こったようですが、インドや中国にもない、日本のみで行われる年中行事です。春・秋のお彼岸、夏のお盆と年に3回あるわけで、先祖を敬い、思いを馳せることは、私たち日本人にとってとても大切なことなのです。
今回は、十五夜とお彼岸のお供え物として月見団子とおはぎの2品をご紹介します。それぞれの解説は写真からご覧ください。
 |
月見団子 十五夜では、月に似せて丸く作った団子15個を山形に盛って、月が見える場所にお供えします。地方によって、ピラミッド型に盛ったり、里芋に似せたりと、さまざまな形状があります。 |
 |
 |
おはぎ お彼岸におはぎをお供えする由来は諸説ありますが、その一つが、小豆の赤い色には魔除けの効果があると古くから信じられており、邪気を払う食べ物としてご先祖様にお供えされてきました。春と秋の両方の季節で食べられます。 |
 |