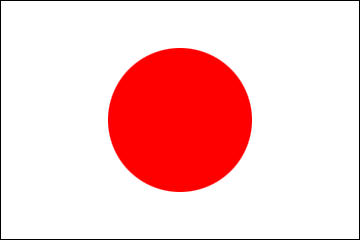【大使活動報告】トポルチャニ市への訪問(3)(2021年10月5日(火)):大モラビア王国の遺物を見学
令和3年10月7日
引き続き、トポルチャニ市のジエッチオーヴァ市長に、近郊のボイニャにある、大モラビア王国考古学博物館を案内してもらいました。博物館の上階はボイニャの町役場になっており、町長にも歓迎頂きました。
大モラビア王国とは、9世紀ごろに、現在のスロバキア西部、チェコ、オーストリア、ハンガリー北部を領域として成立した、スラブ民族による大王国です。その中心地は、現在のスロバキアのニトラ付近であったと考えられています。スラブ系のスロバキアの歴史は、この大モラビア王国時代から始まる、と言われています。ボイニャの川上をたどった山中に、その時代の集落及び城塞の遺跡があり、現在も発掘調査が継続中です。ボイニャの考古学博物館にはその出土品が陳列されています。
スラブ系の国々では、9世紀後半に、(今の)ギリシャ出身のキリル(スロバキアではシリル)とメトディウスの兄弟が、ビザンツ帝国皇帝の命でモラビアに派遣されて、キリスト教を普及したということが歴史的重要性を持っています。スラブ系の国々で今も使われるキリル文字は、この伝道師兄弟のキリルの弟子たちが完成させたものだからです。今も多くのスラブ系の国で、この兄弟をたたえる日が祝日になっています。
しかし、ボイニャの遺跡からは、キリルとメトディウスの伝道前から、大モラビア王国でキリスト教が信仰されていたことを示す物証が発掘されています。祭壇を飾っていたと考えられる天使の彫刻が施された金箔の銅板や、今も音色を出す銅の鐘などです。スラブの国々におけるキリスト教信仰の古さを証明する場所が、スロバキアのこの小さな集落、ボイニャだ、ということになっています。
この事実にどれくらい感動するかは人それぞれだと思いますが、バルカン半島からロシアまで広がるスラブ圏の中ではとても重要な歴史的事実です。ボイニャの町長は、出土した銅の鐘のレプリカを作成し、バチカンにて、ローマ教皇フランシスに献上することが出来た、というほどの重要性を持つのです。
ニトラ北部のトポルチャニ周辺は、ニトラ川の両岸に広がるなだらかな、のどかな丘陵地帯です。スロバキアの観光ガイドにすら大きな記載はありませんが、スロバキアの歴史を語る上では欠くことが出来ない物語を秘めている場所であることが理解できた一日でした。御招待いただいたトポルチャニ市に御礼を申し上げます。
大モラビア王国とは、9世紀ごろに、現在のスロバキア西部、チェコ、オーストリア、ハンガリー北部を領域として成立した、スラブ民族による大王国です。その中心地は、現在のスロバキアのニトラ付近であったと考えられています。スラブ系のスロバキアの歴史は、この大モラビア王国時代から始まる、と言われています。ボイニャの川上をたどった山中に、その時代の集落及び城塞の遺跡があり、現在も発掘調査が継続中です。ボイニャの考古学博物館にはその出土品が陳列されています。
スラブ系の国々では、9世紀後半に、(今の)ギリシャ出身のキリル(スロバキアではシリル)とメトディウスの兄弟が、ビザンツ帝国皇帝の命でモラビアに派遣されて、キリスト教を普及したということが歴史的重要性を持っています。スラブ系の国々で今も使われるキリル文字は、この伝道師兄弟のキリルの弟子たちが完成させたものだからです。今も多くのスラブ系の国で、この兄弟をたたえる日が祝日になっています。
しかし、ボイニャの遺跡からは、キリルとメトディウスの伝道前から、大モラビア王国でキリスト教が信仰されていたことを示す物証が発掘されています。祭壇を飾っていたと考えられる天使の彫刻が施された金箔の銅板や、今も音色を出す銅の鐘などです。スラブの国々におけるキリスト教信仰の古さを証明する場所が、スロバキアのこの小さな集落、ボイニャだ、ということになっています。
この事実にどれくらい感動するかは人それぞれだと思いますが、バルカン半島からロシアまで広がるスラブ圏の中ではとても重要な歴史的事実です。ボイニャの町長は、出土した銅の鐘のレプリカを作成し、バチカンにて、ローマ教皇フランシスに献上することが出来た、というほどの重要性を持つのです。
ニトラ北部のトポルチャニ周辺は、ニトラ川の両岸に広がるなだらかな、のどかな丘陵地帯です。スロバキアの観光ガイドにすら大きな記載はありませんが、スロバキアの歴史を語る上では欠くことが出来ない物語を秘めている場所であることが理解できた一日でした。御招待いただいたトポルチャニ市に御礼を申し上げます。
 |
 |
 |