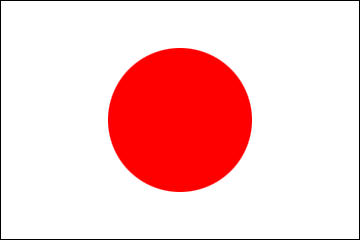二十四節気ごはん10月
令和3年10月15日
二十四節気では、10月は寒露(草木の露が冷たい空気で凍りそうになるほど寒くなる)と霜降(露が冷気で霜となって降り、紅葉が始まる)で、各地で赤や黄色に色づいた美しい紅葉を愛でるために、家族や友人らと紅葉狩りに出かけます。日本列島の北部では10月から紅葉が見ごろになります。
10月は他の月と比べて年中行事が少ない月ですが、日本の10月は、海の幸、山の幸が旬を迎え、食べ物が大変美味しく味わえる季節です。海の幸では、サンマに脂がのって大変美味しくなり、かつ、沢山水揚げされるので、日本の秋を代表する魚となっています。また、秋サケが産卵のために生まれ故郷の川への遡上を始めるので、サケ漁も盛んになります。山の幸では、梨、ぶどう、柿、栗などの果物が最盛期を迎えるほか、マツタケなど、さまざまな秋のキノコ類が沢山並びます。このように、日本の10月は、美味しい食べ物があふれる、豊かな季節です。
10月に関連する話題をもう一つ。150年ほど前まで使われていた陰暦、つまり月齢に基づく暦では、10月は「神無月」(かんなづき)と呼ばれ、漢字の意味は「神がいない月」ということです。これは古来、年に一度10月に、全国の神々が出雲(島根県出雲市)に集まると言われ、出雲以外の土地では神様が不在になるためこのような呼び方になりました。逆に、その時期に神々が集う出雲の地では、10月を「神在月」(かみありつき:神様がいる月という意味)と呼びます。
今回は、日本の秋を代表する味覚として、栗ご飯、サンマの塩焼きと木の子の土瓶蒸しをご紹介します。

旧暦10月に神々が集まると言われている出雲大社


秋刀魚の塩焼き
秋の刀の魚、と書くサンマは、その名のとおり、日本刀のように細長く銀色に輝く青魚で、秋に最も脂がのって美味しくなります。

木の子の土瓶蒸し
土瓶蒸し…土瓶の中に具材を入れ、出汁を張って蒸す料理。
一般的な食べ方としては、土瓶から猪口(小型の器)に汁を注ぎ、吸い物風に出汁を味わいます。添えてある柑橘果汁で味の変化を楽しみ、土瓶の中の具材とともに季節の味を堪能します。
日本ではきのこの種類がとても多いのですが、「香り松茸、味しめじ」という言葉があります。これは、日本に数あるきのこの中で最も香りが良いのが松茸、味が良いのが(ほん)しめじという意味です。

栗ご飯
白米に剥いた栗を入れて一緒に炊き込んだご飯です。
スロバキア同様に、日本でも栗は秋の味覚です。また、秋は新米の季節でもあり、新米で頂く栗ご飯は格別な美味しさです。
10月は他の月と比べて年中行事が少ない月ですが、日本の10月は、海の幸、山の幸が旬を迎え、食べ物が大変美味しく味わえる季節です。海の幸では、サンマに脂がのって大変美味しくなり、かつ、沢山水揚げされるので、日本の秋を代表する魚となっています。また、秋サケが産卵のために生まれ故郷の川への遡上を始めるので、サケ漁も盛んになります。山の幸では、梨、ぶどう、柿、栗などの果物が最盛期を迎えるほか、マツタケなど、さまざまな秋のキノコ類が沢山並びます。このように、日本の10月は、美味しい食べ物があふれる、豊かな季節です。
10月に関連する話題をもう一つ。150年ほど前まで使われていた陰暦、つまり月齢に基づく暦では、10月は「神無月」(かんなづき)と呼ばれ、漢字の意味は「神がいない月」ということです。これは古来、年に一度10月に、全国の神々が出雲(島根県出雲市)に集まると言われ、出雲以外の土地では神様が不在になるためこのような呼び方になりました。逆に、その時期に神々が集う出雲の地では、10月を「神在月」(かみありつき:神様がいる月という意味)と呼びます。
今回は、日本の秋を代表する味覚として、栗ご飯、サンマの塩焼きと木の子の土瓶蒸しをご紹介します。

旧暦10月に神々が集まると言われている出雲大社


秋刀魚の塩焼き
秋の刀の魚、と書くサンマは、その名のとおり、日本刀のように細長く銀色に輝く青魚で、秋に最も脂がのって美味しくなります。

木の子の土瓶蒸し
土瓶蒸し…土瓶の中に具材を入れ、出汁を張って蒸す料理。
一般的な食べ方としては、土瓶から猪口(小型の器)に汁を注ぎ、吸い物風に出汁を味わいます。添えてある柑橘果汁で味の変化を楽しみ、土瓶の中の具材とともに季節の味を堪能します。
日本ではきのこの種類がとても多いのですが、「香り松茸、味しめじ」という言葉があります。これは、日本に数あるきのこの中で最も香りが良いのが松茸、味が良いのが(ほん)しめじという意味です。

栗ご飯
白米に剥いた栗を入れて一緒に炊き込んだご飯です。
スロバキア同様に、日本でも栗は秋の味覚です。また、秋は新米の季節でもあり、新米で頂く栗ご飯は格別な美味しさです。