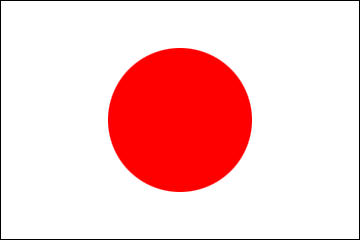二十四節気ごはん3月
令和3年3月5日
3月は二十四節気では、啓蟄(冬眠していた虫が出てくる)、春分(昼と夜の長さが同じになる)で、多くの生き物が春の訪れを感じ、少しずつ活動を始める時期です。
本日3月3日には「ひな祭り」という、ひな人形を飾って女の子の健やかな成長を願う年中行事があります。女の子が生まれると、両親や祖父母がひな人形のお飾りを買いそろえ、毎年3月3日に飾って祝うことが一般的です。
「雛(ひな)」とは小さくて可愛いものという意味で、日本語では生まれたばかりの鳥を「ヒナ」と呼びます。「ひな祭り」の由来は平安時代の京都まで遡ると考えられますが、はっきりした起源はよくわかっていません。平安時代には公家子女の間で「ひいなあそび」という小さな人形を使ったおままごと遊びが流行っていたことは「源氏物語」にも描かれていますが、これは日常生活での遊びであり、時期を決めた特別な年中行事ではありませんでした。
一方、そのころには大陸から伝わった五節句のひとつである「上巳(じょうし)の祓い」(旧暦の3月3日)の行事が定着しており、草木や紙で作った人形(ひとがた)で自分の体をなでて自分の厄を移し、それを水に流して、自分の身を清浄にする(祓う)ということが行われていました。この上巳の祓いで使われた「ひとがた」と「ひいなあそび」の人形が時間の経過のなかで融け合って、現在のように3月3日に雛人形を飾って女の子の健やかな成長を願う年中行事に変化してきたものと考えられています。
また、昔は乳幼児の死亡率が高かったため、子供の無事な成長を願う親は、紙で作った人形を子供の形代(人間の身代わりに厄や穢れを遷すもの)として川に流して厄を払う「ひな流し」という儀式を行っていました。この「ひな流し」も「ひな祭り」の起源の一つになっているとも言われています。現在でも「ひな祭り」の時期に「ひな流し」を行う地域もあります。
女の子を祝う日であるひな祭りでは、可愛らしい手毬寿司やハマグリのお吸い物、3色のひし餅、ひなあられが食べられます。それぞれのお料理の写真に解説がついているのでご覧ください。
過去の二十四節気ごはんシリーズの記事は当館HPからご覧になれます。
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00181.html
本日3月3日には「ひな祭り」という、ひな人形を飾って女の子の健やかな成長を願う年中行事があります。女の子が生まれると、両親や祖父母がひな人形のお飾りを買いそろえ、毎年3月3日に飾って祝うことが一般的です。
「雛(ひな)」とは小さくて可愛いものという意味で、日本語では生まれたばかりの鳥を「ヒナ」と呼びます。「ひな祭り」の由来は平安時代の京都まで遡ると考えられますが、はっきりした起源はよくわかっていません。平安時代には公家子女の間で「ひいなあそび」という小さな人形を使ったおままごと遊びが流行っていたことは「源氏物語」にも描かれていますが、これは日常生活での遊びであり、時期を決めた特別な年中行事ではありませんでした。
一方、そのころには大陸から伝わった五節句のひとつである「上巳(じょうし)の祓い」(旧暦の3月3日)の行事が定着しており、草木や紙で作った人形(ひとがた)で自分の体をなでて自分の厄を移し、それを水に流して、自分の身を清浄にする(祓う)ということが行われていました。この上巳の祓いで使われた「ひとがた」と「ひいなあそび」の人形が時間の経過のなかで融け合って、現在のように3月3日に雛人形を飾って女の子の健やかな成長を願う年中行事に変化してきたものと考えられています。
また、昔は乳幼児の死亡率が高かったため、子供の無事な成長を願う親は、紙で作った人形を子供の形代(人間の身代わりに厄や穢れを遷すもの)として川に流して厄を払う「ひな流し」という儀式を行っていました。この「ひな流し」も「ひな祭り」の起源の一つになっているとも言われています。現在でも「ひな祭り」の時期に「ひな流し」を行う地域もあります。
女の子を祝う日であるひな祭りでは、可愛らしい手毬寿司やハマグリのお吸い物、3色のひし餅、ひなあられが食べられます。それぞれのお料理の写真に解説がついているのでご覧ください。
過去の二十四節気ごはんシリーズの記事は当館HPからご覧になれます。
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00181.html
 |
 |
|
伝統的なひな人形一式。ひな祭りでは, |
「ひな流し」に使用される人形。 |
 |
 |
| 手毬寿司 平安時代に保存食として食されたなれ寿司に、 華やかな具材を足したちらし寿司を食 べるようになったのが始まりです。 今では、そのちらし寿司を丸くして、 華やかで可愛らしい手毬の形に仕上げた寿司 が人気です。 |
|
 |
 |
|
日本の伝統的な手鞠です。 |
ハマグリのお吸い物 ハマグリのような二枚貝は、決まった対の 貝殻でないとピッタリと合わないため「夫婦円満」 の象徴とされ、平安時代にはハマグリの 貝殻は「貝合わせ」という遊びに使われていました。 このような特徴から、一人の相手と一生 仲良く過ごすという良縁を願って食べられるよ うになりました。スロバキアではハマグ リが入手できないため、 今回はアサリを代用しています。 |
 |
 |
| 平安時代の貝合わせ 対の貝殻の内側に同じ絵が描かれています。 たくさんの貝殻の中から、 より多くの対の貝殻を見つけた人が勝ちです。 |
ひし餅 ひし餅の色は緑、白、赤の3色です。 |
 |
|
|
ひなあられ 昔、ひな人形に外の景色を見せる遊び |