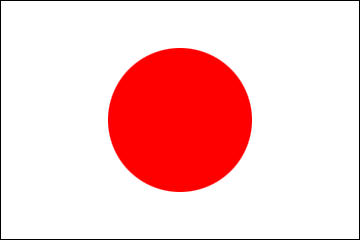季節の変化と旬から見える人々の暮らし「二十四節気ごはん」
令和3年9月20日
日本には、はっきりとした四季があります。季節ごとに花が咲き、木々が色付き、雪が降り、食材は旬を迎えます。日本人はその美しい自然の移り変わりを、24の季節に分けて愛でてきました。この「二十四節気ごはん」シリーズでは、今後1年間(二十四節気)を通じて、自然の変化とそれに根ざす人々の感性や伝統を、その季節の代表する日本料理・和菓子とともに伝えていきます。
なお、料理・菓子の紹介では、日本大使館公邸料理人の石森秀明料理人に監修・制作していただきます。
なお、料理・菓子の紹介では、日本大使館公邸料理人の石森秀明料理人に監修・制作していただきます。
石森秀明料理人について:1981年生まれ。2001年4月より(株)プリンスホテルにて勤務、日本料理を担当。2020年7月から在スロバキア日本国大使館の公邸料理人として従事。
二十四節気は、太陽の黄道を24等分したもので、1季節は15日間になります。それぞれに季節の名前があり、農作業などの目安にされました。この二十四節気は中国で設立され、日本には平安時代に伝わったと言われています。
 |
二十四節気一覧(各月の伝統行事や料理等を紹介します)