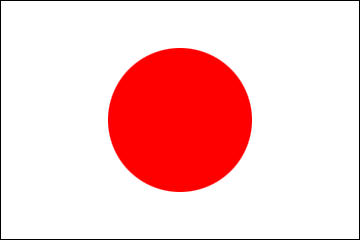二十四節気ごはん5月
令和3年5月4日
二十四節気では、5月は立夏(夏の始まり)と小満(秋に撒いた麦の穂がつき始めることから、少し満足する)で、晴れ晴れとした暖かい日が多くなり、洋服や家の衣替えをして、これからますます暑くなる時期に向けて準備をします。
5月5日は、奈良時代(西暦700年頃)に大陸から伝わった五節句のひとつである「端午の節句」にあたります。季節の節目である端午の節句は、奈良・平安時代では、災いを避けるための行事が行われる重要な日でした。宮廷では、魔除けの薬草である菖蒲(しょうぶ)を軒に挿し、臣下らは厄災を追い払うために馬射(うまゆみ)や競馬(くらべうま)をしたそうです。
やがて政治勢力の中心が貴族から武家に移ると、端午の節句で魔除けとして使用された菖蒲(しょうぶ)の音が、武を尊ぶという意味の尚武(しょうぶ)と同じであることから、「端午の節句」は「尚武の節句」として武家の間で盛んに祝われるようになりました。こうして、端午の節句は、家の後継ぎとして生まれた男子が、無事に成長することを祈り、一族の繁栄を願う重要な行事となりました。
端午の節句では、鎧や兜、鯉のぼりを飾りますが、鎧や兜を飾ることは、武家社会から生まれた風習です。鎧兜は、武士にとって自分の命を守る神聖なもので、神社にお参りに行く際には、鎧兜を奉納して身の安全,厄払いをしたそうです。端午の節句では、大切な子どもを守ってくれるようにとの願いを込めて鎧兜を飾ります。また、鯉は生命力が強く、清流を遡って滝を登ると竜になるという伝説にちなみ、子どもがどんな環境でも耐え、立派な人になることを願って、鯉のぼりは飾られます。
端午の節句では、ちまき寿司とかしわ餅がよく食べられます。また、春が旬である鯛を利用した兜煮もご紹介します。それぞれのお料理のご紹介は写真からご覧になれます。
過去の二十四節季ごはんの記事はこちらからご覧下さい。
5月5日は、奈良時代(西暦700年頃)に大陸から伝わった五節句のひとつである「端午の節句」にあたります。季節の節目である端午の節句は、奈良・平安時代では、災いを避けるための行事が行われる重要な日でした。宮廷では、魔除けの薬草である菖蒲(しょうぶ)を軒に挿し、臣下らは厄災を追い払うために馬射(うまゆみ)や競馬(くらべうま)をしたそうです。
やがて政治勢力の中心が貴族から武家に移ると、端午の節句で魔除けとして使用された菖蒲(しょうぶ)の音が、武を尊ぶという意味の尚武(しょうぶ)と同じであることから、「端午の節句」は「尚武の節句」として武家の間で盛んに祝われるようになりました。こうして、端午の節句は、家の後継ぎとして生まれた男子が、無事に成長することを祈り、一族の繁栄を願う重要な行事となりました。
端午の節句では、鎧や兜、鯉のぼりを飾りますが、鎧や兜を飾ることは、武家社会から生まれた風習です。鎧兜は、武士にとって自分の命を守る神聖なもので、神社にお参りに行く際には、鎧兜を奉納して身の安全,厄払いをしたそうです。端午の節句では、大切な子どもを守ってくれるようにとの願いを込めて鎧兜を飾ります。また、鯉は生命力が強く、清流を遡って滝を登ると竜になるという伝説にちなみ、子どもがどんな環境でも耐え、立派な人になることを願って、鯉のぼりは飾られます。
端午の節句では、ちまき寿司とかしわ餅がよく食べられます。また、春が旬である鯛を利用した兜煮もご紹介します。それぞれのお料理のご紹介は写真からご覧になれます。
過去の二十四節季ごはんの記事はこちらからご覧下さい。
 |
五月人形 端午の節句の内飾りとして、鎧飾りや兜飾り、子供の武将人形など種類がありますが、総じて五月人形と言われています。 |
|
 |
鯉のぼり 鯉のぼりは端午の節句の外飾りです。江戸時代(西暦約1600年~1870年)、将軍に男子が生まれると、のぼりを立てて祝いました。町人の間では武家ののぼりの代わりに、鯉のぼりを飾ったのが始まりだそうです。 |
|
 |
かしわ餅 かしわは、新芽が育つまで古い葉は落ちないことから、「後継ぎが絶えない」「子孫繁栄」のシンボルとされています。あんこ入りのお餅をかしわの葉で包んだ和菓子です。 |
|
 |
ちまき寿司 ちまきは、邪気を払うとされる笹の葉で寿司を包んだものです。古代中国の物語から、忠誠心のある立派な人間に育つことを願い、子どもにちまきを食べさせる風習があります。 |
|
 |
鯛の兜煮 日本では、魚の頭を「兜」とも表現し、鎧兜を飾る端午の節句の縁起の良い料理として、鯛の兜煮は食べられます。 |